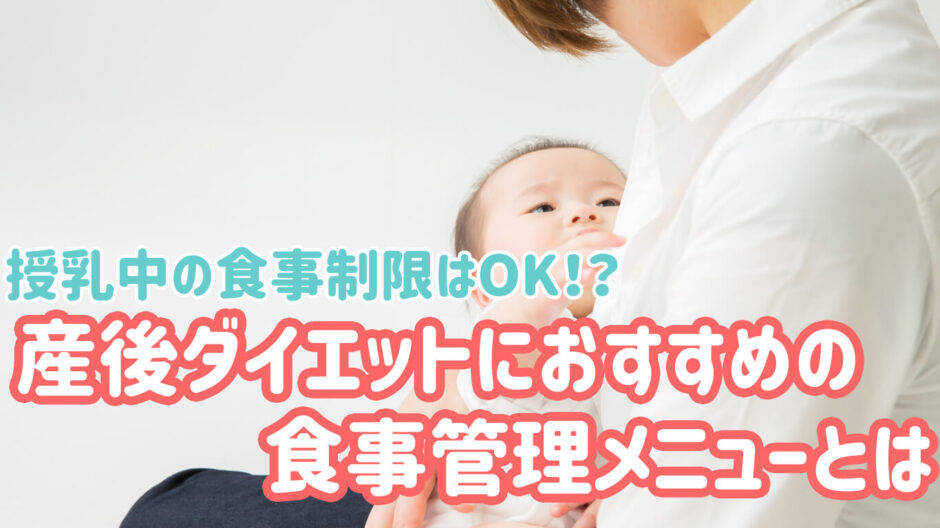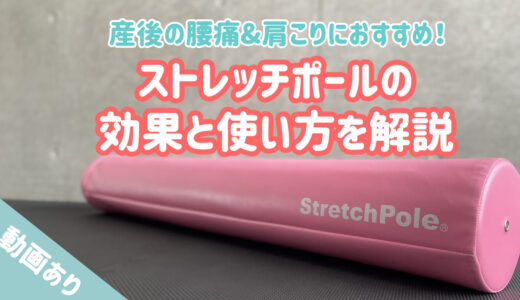「出産後の体重がなかなか減らずに悩んでいる、、、」
「授乳中に食事や糖質制限をしてもいいのか知りたい、、、」
「産後ダイエットにおすすめの食事管理法を知りたい!」
このように、出産後の体重が思うように落ちず食事制限や運動で産後ダイエットに励むママさんは多いですよね。
しかし、まだ授乳中にも関わらず食事制限を行って良いのか悩んでいるママさんも少なくないず。
そこで今回は、授乳中ママ向けに産後ダイエットにおすすめの食事管理メニューをご紹介します!

mamaトレタイムズ編集部の佐藤です!今回は、私が実際に産後ダイエットをサポートさせていただいている経験やお客様の成功事例なども踏まえて解説していきます♪

mamaトレタイムズ編集部
佐藤 誠
パーソナルトレーナー
パーソナルトレーナー歴15年。トレーナーとして活動しながら、女性向けパーソナルトレーニングジムのプロデュースや企業向けレッスンを提供するなど幅広く活動。そして、自身が父親になったことをきっかけに、ママさん達の大変さや産後のカラダに対する悩みが多いことを痛感し、mamaトレを立ち上げる。【保有資格】健康連動実績指導者/タイ政府公認タイ伝統医療協会認定タイ古式マッサージセラピスト/子ども身体運動発達指導士/介護予防予防連動指導員etc
【PR】産後ダイエット専門オンライントレーニング|mamaトレ

mamaトレ(ママトレ)は、産後ダイエット専門オンラインパーソナルトレーニングジムです。
スマホがあれば自宅にいながらパーソナルトレーナーとのマンツーマンでレッスンが受けれます!
産後ダイエットはもちろん、産後の骨盤調整や姿勢改善など産後ママが抱えるカラダの悩みに経験豊富なトレーナー陣がサポートしていきます。
無料体験レッスン実施中
- 月額6,600円(税込)〜始められる
- スマホがあれば自宅で簡単に受けられる
- 当日キャンセルや当日予約もOK!子どもの急な体調不良でも安心
授乳中の食事制限や糖質制限はOK?

まずはじめに、授乳中に産後ダイエットを行う際に気になるのが食事制限や糖質制限を行っても良いのかどうかではないでしょうか。
結論からお伝えすると、授乳中の食事制限や糖質制限はおすすめできません。
その理由としては、過度な食事制限や糖質制限を無理して行わなくても体重が落ちる可能性が高いからです。
妊娠中から出産後はホルモンバランスの影響で脂肪がつきやすいカラダになっています。
しかし、出産後徐々にホルモンバランスの変化により脂肪が落ちやすい状態になっていきます。
また、食事をバランスよくしっかり食べて育児による心身の疲労を回復させる必要もあります。
過度な食事制限で体調を崩して、育児に支障をきたすのは一番避けたいですよね。

私の経験則ではありますが、産後に体重が落ちずに悩んいるママさんは食事や間食を食べ過ぎていることが多いです。しかし、授乳中は食べても食べてもお腹が空いてしまうのが実情ですよね、、、
産後のカラダの反応としては自然なため、だからこそ一度食習慣を見直す機会を設けることも大切だと思います。
授乳中の摂取カロリー目安
授乳中の食事制限がおすすめできない理由として、厚生労働省が公表している「日本人の食事摂取基準」※1を見ても分かります。
「日本人の食事摂取基準」によると、授乳中は一般女性に比べ摂取カロリーを350kcal増やすことが推奨されています。
このように、授乳中は食事制限どころか一般女性に比べて多く食べることが推奨されています。
しかし、好きなものをたくさん食べて良いという話ではなくバランスの良い食事をしっかり食べることが重要です。
授乳中は痩せる?産後ダイエットを始めるおすすめの時期とは

授乳中は痩せると聞いたことがあるママさんは多いと思いますが、実際のところどうなのでしょうか。
先ほど、授乳中のママさんは一般女性よりもカロリー摂取する必要があるとお伝えしました。
別の言い方をすると、一般女性よりも多くエネルギーを消費するからカロリーを多く摂取する必要があると言うこともできるでしょう。
また、妊娠中はホルモンバランスの影響で脂肪がつきやすい状態になっていますが出産後は徐々に脂肪が落ちやすいカラダの状態にもなっていきます。
このような理由から、授乳中は痩せやすい時期であると言われています。
離乳食が始まり母乳を飲ませる頻度が少なくなってくる産後6ヶ月以内が産後ダイエットにはおすすめの時期と言えます。

産後1ヶ月くらいは産褥期でもあるのでしっかりカラダを休めましょう♪そして、産後2~3ヶ月頃から徐々にストレッチや筋トレなどを始めてみて、それでも体重が落ちないようでしたら産後4~5月目から食事管理をしてみるのがおすすめです!
産褥期(さんじょくき)とは、出産後、体が妊娠前の状態に戻るまでの期間を言います。 その期間は人によって変わるのですが、一般的に6~8週間ほどかかります。 妊娠出産は女性にとってとても大きな体の変化を伴うのですが、産褥期の間にゆっくりとホルモンバランスが徐々に妊娠前に戻り、子宮の大きさも徐々に小さくなっていきます。
産後ダイエットは何から始める?やるべきことをスケジュール別にご紹介
授乳中の産後ダイエットにおすすめの食事管理メニューとは

ここからは、授乳中の産後ダイエットにおすすめの食事管理メニューについてお伝えしていきます。
ここまでお伝えした通り、授乳中はしっかりとカロリーを摂取しながらダイエットを行う必要があります。
下記のポイントを参考にしていただき、バランスの良い食事メニューをしっかり食べながら母子ともに元気に産後ダイエットを成功させましょう。
PFCバランスを意識する
授乳中はバランスの良い食事をしっかり食べるとお伝えしましたが、そもそもバランスの良い食事とはどのような食事なのでしょうか。
バランスの良い食事を表す際によく使われる指標として、PFCバランスという考え方があります。
PFCバランスとは、三大栄養素であるProtein(タンパク質)とFat(脂質)、Carbohydrate(炭水化物)の頭文字から表されています。
この三大栄養素が、食事のどれくらいの割合を占めるかを示した比率のこと。
PFCバランスは目的に応じて比率が多少変動しますが、目的に応じたPFCバランスに適応した食事をバランスの良い食事と言うことができるでしょう。
「日本人の食事摂取基準」によると、授乳中の食事のPFCバランスは下記のようなバランスが推奨されています。
P(タンパク質)=15~20% F(脂質)=20~30% C(炭水化物)=50~65%
割合で表してもイメージがつきにくいと思いますので、量(g)に換算し食品を例にしてご紹介します。
- P(20%)=470kcal(118g)→鶏肉400g
- F(20%)=470kcal(52g)→オリーブオイル大さじ4杯
- C(60%)=1410kcal(353g)→ごはん5膳
※タンパク質4kcal/g 脂質9kcal/g 炭水化物4kcal/g

あくまで目安ではありますが、しっかり食べられる印象ではないでしょうか?授乳中はしっかり食べる必要があるからこそ何を食べるかが重要になってきますね!
ここでご紹介したPFCバランスを意識しながら、バランスの良い食事を目指していきましょう。
次は、各栄養素について詳しく解説していきます。
GI値の高い炭水化物は控える
糖質制限ダイエットという言葉を一度は聞いたことがあると思います。
昔はカロリーを抑えることがダイエットに効果的と言われていましたが、最近はカロリーではなく糖質を制限することがダイエットに効果的であると言われるようになってきました。
では、糖質制限とは具体的にどのような方法を指すのでしょうか。
まずはじめに間違えてはいけないのが、「糖質制限=全く糖質を食べない」ということではないと言うことです。
糖質は人間にとってとても重要な栄養素であり、その糖質を過度に制限すると身体活動に支障をきたしてしまいます。
先ほどご紹介したPFCバランスを見ても分かるように、全体の60%を糖質を含む炭水化物から摂取する必要があります。
しかしながら、糖質のコントロールがダイエット成功の鍵を握っているのも事実です。
そのため糖質は上手くコントロールしながら上手に摂取することが重要なのです。
GI値について
では、糖質(炭水化物)を上手に選んで摂取するにはどうしたら良いのでしょうか。
糖質(炭水化物)食品を選ぶ時の一つの指標が、GI値(グライセミック・インデックス)です。
GI値とは、食後の血糖値上昇度合いを示す指標です。
GI値が低い(55以下)食品は、低GI食品と呼ばれ血糖値を緩やかに上昇させます。
逆にGI値が高い(55以下)食品は、高GI食品と呼ばれ血糖値を急激に上昇させます。
血糖値の急激な上昇は、カラダへの負担も大きく肥満やその他の不調に繋がります。
そのため、ダイエット中や健康のためにはできるだけ低GI食品を選ぶようにしましょう。
低GI食品一覧
ダイエットにおすすめ!低GI食品一覧
| 穀類 | 野菜類 | 果物 |
|---|---|---|
| 全粒粉パン(50) | ほうれん草(15) | いちご(29) |
| 全粒粉パスタ(50) | 小松菜(23) | グレープフルーツ(31) |
| そば(54) | 大根(26) | キウイ(35) |
| オートミール(55) | トマト(30) | りんご(36) |
| 玄米(55) | さつまいも(55) | バナナ(55) |
脂質は選んで摂取する
脂質は大きく二つに分けると、カラダにとって悪い脂質(飽和脂肪酸)と良い脂質(不飽和脂肪酸)に分けられます。
一般的に言われている悪い脂質(飽和脂肪酸)は、お肉や乳製品などに多く含まれている脂質で中性脂肪などを上昇させるためダイエットには天敵です。
一方、良い脂質(不飽和脂肪酸)はオリーブオイルや魚に多く含まれており、中性脂肪などを下げダイエットの手助けをしてくれます。
しかし、良い脂質(不飽和脂肪酸)もカロリーが高ことに変わりはありませんので摂り過ぎには注意が必要です。
脂質を多く含む食品一覧
悪い脂質・良い脂質を含む食品一覧
| 悪い脂質(飽和脂肪酸) | 良い脂質(不飽和脂肪酸) |
|---|---|
| バター・マーガリン | 青魚 |
| 乳製品 | えごま油・ごま油 |
| 牛脂 | オリーブオイル |
| パーム油 | アーモンド(ナッツ類) |
| ココナッツオイル | アボカド |
タンパク質の摂取を心がける
タンパク質はダイエットやボディメイクにおいてとても重要ですが、授乳中も普段より多く摂取することが推奨されています。
「日本人の食事摂取基準」によると、授乳中は一般女性に比べタンパク質を20g/日多く摂取するよう推奨しています。
先ほどお伝えした、PFCバランスなどを踏まえてもタンパク質を1日100g程度を目標に摂取するようにしましょう。
タンパク質を多く含む食品一覧
タンパク質を多く含む食品一覧
| 動物性タンパク質 | 植物性タンパク質 |
|---|---|
| しらす(半乾燥)(40g) | きな粉(36g) |
| まぐろ(赤身)(25g) | 納豆(17g) |
| ささみ(23g) | 枝豆(11g) |
| 牛肉・豚(ヒレ)(20g) | 木綿豆腐(7g) |
| 卵(20g) | 豆乳(4g) |
産後ダイエットにおすすめの野菜や果物
ここまでご紹介した三大栄養素(炭水化物・脂質・タンパク質)にビタミンとミネラルを足して五大栄養素とも言われています。
ビタミンとミネラルも人間にとってとても重要な栄養素なため、ここからは産後に重要なビタミンとミネラルについてご紹介していきます。
特に授乳中に重要とされているビタミンDは、母子ともに不足しがちなビタミンと言われています。
ビタミンDが不足すると、子どもの場合は「くる病」やO脚の原因、大人の場合は「骨軟化症」のリスクが高まると言われています。
ビタミンDに関しては、日光浴でも増やすことができるので適度に日に当たる時間を作ることも大切です。
もちろんビタミンD以外にも重要なビタミンばかりですので、ビタミンとミネラルの働きと多く含む食品を下記にまとめてご紹介します。
産後におすすめのビタミン・ミネラルを多く含む食品一覧
ビタミン・ミネラルを多く含む食品一覧
| 主なメリット | 多く含む食品 | |
|---|---|---|
| ビタミンD | くる病や低カルシウム症の予防に効果的 | きくらげ/しいたけ/まいたけ エリンギ/えのき |
| ビタミンB群 | 各栄養素の代謝 | 豚肉/レバー/貝類 |
| ビタミンC | 抗酸化作用 | キウイ/イチゴ ブロッコリー/ピーマン |
| 鉄 | 貧血防止 | レバー/カツオ/小松菜 ほうれん草/ひじき |
| カルシウム | 骨と歯の強化 | 乳製品/いわし/煮干し |
授乳中も葉酸の摂取を心がける
妊娠中に葉酸の摂取が推奨されているのをご存知のママさんは多いと思いますが、実は授乳中も葉酸の摂取は推奨されています。
母乳は血液から作られているため、造血作用のある葉酸の摂取が授乳中も推奨されています。
葉酸を多く含む食品
| 葉酸を多く含む食品一覧 |
|---|
| ・焼きのり ・わかめ ・あおさ ・ひじき ・レバー ・たまご ・枝豆 ・ブロッコリー ・ほうれん草 ・アスパラガス |
おやつや間食で栄養補給

ここまでご紹介した、授乳中に必要な栄養素を考慮しつつ産後ダイエットにおすすめのおやつをご紹介します♪育児の息抜きのお供に活用してください!
- 干し芋
- カカオ70%チョコ
- 煮干し
- 素焼きアーモンド
- チーズ
授乳中や産後ダイエット中に食べてはいけないものとは

ここからは、授乳中や産後ダイエット中に控えたい食品をご紹介します。
授乳中に控えたい食品
まずは、産後ダイエットに関わらず授乳中に控えるべきとされている食品をご紹介します。
母乳は血液から作られているため、基本的には母親が食べたものがそのまま母乳になることはありません。
近年、様々な研究でも母親が食べたものが母乳の成分や味に影響は及ぼさないという結果も出ています。
そのため、完全に控える必要はありあせんが摂りすぎには注意しましょう。
- アルコール
- カフェイン含有食品・飲料
- 脂肪分の多い食べ物
産後ダイエット中に控えたい食品
次に、授乳中に関わらず産後ダイエット中に控えたい食品をご紹介します。
- 高GI食品
- 加工品
産後ダイエットを成功させるポイント

最後に、産後ダイエットを成功させるためのポイントをお伝えします。
ダイエットを成功させるには筋トレ以外にも大切なポイントがあるので参考にしてくださいね。
- まずは骨盤の歪みや姿勢の改善から
- ながらトレーニングを意識する
- 水分摂取を心がける
- トレーナーなど専門家のアドバイスを受ける
まずは骨盤の歪みや姿勢の改善から
産後ダイエットや筋トレを行う前に、まずは骨盤の歪みや姿勢を改善するためのストレッチから始めることをおすすめします。
妊娠中や出産後に腰痛や肩こり、腱鞘炎などに悩まされる方はとても多いです。
そのため、まずはストレッチなどでカラダを整えることから始めていきましょう。
ストレッチにもダイエット効果は期待できますし、整ったカラダで筋トレを行うことでケガのリスクを減らせ、さらにはトレーニング効果も高まるので一石三鳥です!
産後におすすめのストレッチはこちらの記事を参考にしてください。
ながらトレーニングを意識する
産後は育児や家事に追われ、筋トレをする時間を確保するのも難しいと思います。
そのため、テレビを観ながらや子どもを寝かしつけながらなど、上手く生活に組み込みながら筋トレの時間を確保できるといいですね。
代謝を上げる観点から考えても、筋トレをする時間を小分けに確保するのがおすすめです。
例えば、週1回60分のトレーニングより、週4回15分のトレーニングの方がおすすめ。
極端な食事制限は行わない
産後ダイエットに限らず、ダイエットを成功させる大切なポイントになってくるのが食事です。
しかし、現在授乳中の方は食事制限は行わない方がいいでしょう。そして、授乳が終わった方も極端な食事制限はおすすめしません。
理由としては、育児による心身への疲労をバランスの良い食事でケアする必要があります。
育児に休みはないため、ママさんは体調不良になれませんからね。
食事制限なし=お菓子を食べてもいいということではありませんので(笑)
食べすぎないバランスの良い食事を心がけましょう。
水分摂取を心がける
水をたくさん飲むことは、ダイエットにも美容にもとてもおすすめです。
水を飲むことにより、血液循環が良くなりカラダ全体の代謝が良くなります。
1日2リットル程度を目標に、小まめに水を飲むことを心がけましょう。
お茶などでも問題ありませんが、お茶などには利尿作用もあるため、できれば水を飲んで頂くことをおすすめします。
トレーナーなど専門家のアドバイスを受ける
可能であればトレーナーなどダイエットやボディメイクの専門家のサポートを受けることをおすすめします。
特に最初が肝心なので、できれば早い段階でカラダの状態をチェック<してもらったり、正しいトレーニングフォーム<を教えてもらうなど、あなたに合ったトレーニング方法を教えてもらうのが一番の近道だと思います。
そして、三日坊主にならないためにもサポート役の存在はとても重要です。
最近では、オンラインでのパーソナルトレーニングも増えてきていたり、子連れで通えるジムもあるので一度検討してみてはいかがでしょうか?
産後ダイエットの注意点

最後に、産後ダイエットや産後に運動を行う際の注意点をお伝えします。
安全かつ、健康的に産後ダイエットを行うためにダイエットや運動をはじめる時期と注意点について確認しておきましょう。
産後ダイエットをはじめる時期
出産直後のカラダは、妊娠や出産により相当のダメージを負っています。
また、赤ちゃんの夜泣きや授乳で疲労し、ダイエットや運動どころではないかもしれません。
そのため、産褥期は安静に過ごし担当医と相談しながら産後2~3ヶ月目頃から徐々に軽い運動(ストレッチやウォーキング)からはじめるのがおすすめです。
産後ダイエットを行う上での注意点
- 出産直後の激しい運動や過度な食事制限は控えましょう
- まずはウォーキングやストレッチなど軽い運動からはじめましょう
- 日々の体調変化に気をつけて体調が悪い時は無理に行わないようにしましょう
- 授乳中は食事制限に頼り過ぎず、運動中心のダイエットを行いましょう
産後ダイエットは焦ったり、無理をするのは禁物です。ママさんと赤ちゃんの健康を第一に考え、マイペースに行なっていくことをおすすめします。
出産直後は気分転換を兼ねて軽い運動からはじめ、心身ともに余裕が出てきたら本格的にダイエットを始めてみてはいかがでしょうか。
まとめ
今回は授乳中の産後ダイエットにおすすめの食事メニューについてご紹介しました。
授乳中はもともと体重が落ちやすい時期でもあります、そのためまずは食べ過ぎないことに気をつけバランスの良い食事と適度な運動で妊娠前のの体重に戻していきましょう。
何よりもママさんの体調と子育てを最優先に、赤ちゃんとの1日1日を大切にしてくださいね。
<参考>
※1 日本人の食事摂取基準
※2 母乳の味はお母さんの食事で変わる?(医療ガバナンス会)
※3 母乳だけで育つ乳児の75%がビタミンD不足(日経メディカル)